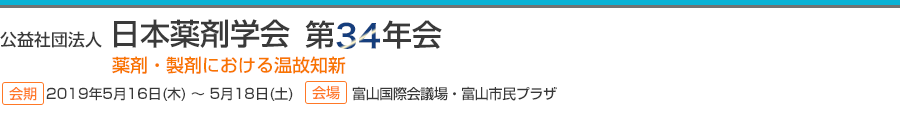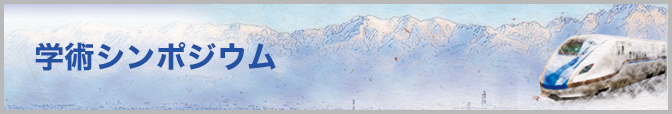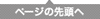第34年会では、以下6件の「学術シンポジウム」を予定しております。
学術シンポジウム 1 Symposium 1
エビデンスに基づく薬物療法の個別化と適正化:薬剤師に何ができるか
- オーガナイザー
- 嶋田 努 (金沢大学附属病院薬剤部)
- 森田 真也 (滋賀医科大学医学部附属病院薬剤部)
分子標的薬や免疫チェックポイント阻害剤など新規メカニズムに基づく薬物が臨床で使われるようになり、従来の薬物を含め患者さんにとって適切な薬物療法の提供のためには、これまで以上に個人差となる個々の患者背景の把握と評価が必要である。本シンポジウムは、「エビデンスに基づく薬物療法の個別化と適正化:薬剤師に何ができるか」をテーマに、プレシジョン・メディシンの現状と展望と、新規分子標的薬や経験に基づく漢方医学に対して、また種々の病態に対してどのような視点からエビデンスに基づく個別化医療を実施していくべきかを、各演者のご講演いただき、薬剤師として何が出来るかを一緒に考えていきたい。
- 薬学的視点に基づいたプレシジョン・メディシン ?現状と展望?
- 寺田 智祐 (滋賀医科大学医学部附属病院薬剤部)
- 構成生薬から考える漢方薬の個別化医療と適正使用の推進 ?明日からの業務に役立つ漢方薬の考え方?
- 加藤 敦 (富山大学附属病院薬剤部)
- 経口がん分子標的薬の個別投与設計に向けた取り組み
- 山口 浩明 (東北大学病院薬剤部)
- 病態背景を考慮した個別化薬物療法に向け -肥満病態を中心に-
- 嶋田 努 (金沢大学附属病院薬剤部)
学術シンポジウム 2 Symposium 2
経肺経鼻投与型製剤の設計と体内動態の評価
- オーガナイザー
- 岡本 浩一 (名城大学薬学部)
- 尾関 哲也 (名古屋市立大学大学院薬学研究科)
経肺経鼻投与製剤は、肺・鼻局所疾患のみならず全身作用薬の投与剤形としても注目されている。全身作用型の経鼻投与製剤はわが国でも実用化されており、バイオ医薬の投与部位として有望である。さらに近年効率的な中枢への薬物送達経路としても期待されている。経肺投与製剤は、肺の構造の複雑さから精密な粒子設計が重要となる。本シンポジウムでは、以上の観点から、経肺経鼻投与型製剤の設計と体内動態の評価について、先端的研究を進めている若手研究者にご講演いただき、今後の経肺経鼻投与製剤開発の方向性について議論する場としたい。本シンポジウムは、日本薬剤学会経肺経鼻投与製剤FGとの共同企画である。
- 経鼻投与による薬物・バイオ医薬の脳内デリバリー動態と中枢疾患治療への応用
- 金沢 貴憲 (日本大学薬学部)
- 膜透過ペプチド固定化高分子を用いたバイオ医薬品の経鼻吸収促進技術の開発>
- 伴野 拓巳 (摂南大学薬学部)
- 肺内でナノ粒子を構成するドラッグデリバリーシステム型吸入粉末剤の開発とその評価
- 奥田 知将 (名城大学薬学部)
- 印刷工学技術の発展的応用による吸入用微粒子設計と生物薬剤学的特性評価
- 佐藤 秀行 (静岡県立大学薬学部)
学術シンポジウム 3 Symposium 3
脳標的デリバリーの萌芽的技術
- オーガナイザー
- 楠原 洋之 (東京大学大学院薬学研究科)
- 出口 芳春 (帝京大学薬学部)
近年の創薬モダリティの多様化に伴い、脳内の薬効標的により特異性の高いペプチド・抗体・遺伝子などの高分子の開発が進められている。しかしながら、物質の脳への移行は血液脳関門(BBB)によって強固に制限されており、高分子はほとんど脳に移行しない。従って、BBBを超えるデリバリー技術の開発が期待されている。本シンポジウムでは、脳へのデリバリー技術の萌芽的研究成果に加え、ヒト脳移行性評価法に関する研究成果を紹介する。
- 高分子の脳デリバリーに資する脳関門透過ペプチドの開発
- 大槻 純男 (熊本大学大学院生命科学研究部(薬学系))
- 血液脳関門を効率的に「越える」ナノマシンの開発
- 安楽 泰孝 (東京大学大学院工学研究科)
- DNA/RNA ヘテロ2本鎖核酸(DNA/RNA heteroduplex oligonucleotide;HDO)の創生
- 横田 隆徳 (東京医科歯科大学脳神経病態学分野)
- 脳移行性評価技術としてのヒトiPS 由来脳毛細血管内皮細胞の有用性と限界
- 出口 芳春 (帝京大学薬学部)
学術シンポジウム 4 Symposium 4
医薬品と医療機器のコンビネーション(DDC)技術及び薬剤投与デバイスの進歩
- オーガナイザー
- 杉林 堅次 (城西大学)
- 森部 久仁一 (千葉大学)
摂取可能なセンサーを組み込んだ処方薬(デジタルメディスン)は、スマートフォンなど情報通信技術(ICT)と組み合わせることで、患者の服薬状況や活動状況の記録、医療従事者との情報共有が可能になるため、これまで実現できなかった遠隔地での服薬管理など幅広い活用が期待される。このような医薬品と医療機器の組み合わせ(Drug-Device Combinations:DDC)による服薬支援デバイスが、近年各種剤形の製剤で研究・開発されている。また、効果的な薬物治療のためには、製剤とデバイスの組み合わせが重要になる剤形がある。本シンポジウムでは、DDCやデジタルヘルス、経皮投与・吸入デバイスに関する最新の知見をもとに、医薬品製剤の現状と今後について考えてみたい。
- 世界初のデジタルメディスン エビリファイマイサイトについて
- 倉橋 伸幸 (大塚ファーマシューティカル D&C Inc.)
- IoTと家庭血圧モニタリング
- 山下 新吾 (オムロンヘルスケア(株))
- 新しい経皮投与技術「Nitto PassPort? System」
- 花谷 昭徳 (Nitto Denko Technical Corporation)
- 治療の最適化に貢献する吸入デバイスの進歩
- 平 大樹 (立命館大学薬学部)
学術シンポジウム 5 Symposium 5
ポストICH M9における薬剤学BE研究
- オーガナイザー
- 佐久間 信至 (摂南大学薬学部)
- 立木 秀尚 (東和薬品(株))
ICH M9:「BCSに基づくバイオウェーバー」のガイドライン策定や国内BEガイドライン改正が進む昨今、BE試験関連の新しい知見が増え、薬剤学BE研究は、規制科学、基礎研究および開発技術など、幅広い知識を統合しての議論が必要な研究領域となった。本シンポジウムでは、医薬品の承認審査、学術研究、新薬開発、ジェネリック医薬品開発と、異なる立場の専門家がポストICH M9を見据えて、ICH M9やBE試験に関する最新知見を題材に討議を行い、より優れた医薬品創出のためのBE試験についての情報提供をおこなう。
- ICH M9:Biopharmaceutics Classification System( BCS)に基づくバイオウェーバー
~新たに導入が検討されている生物学的同等性試験免除の考え方~ - 栗林 秀明 (医薬品医療機器総合機構)
- BCS に基づくバイオウェーバーに関する科学的考察
- 菅野 清彦 (立命館大学薬学部)
- 新薬開発におけるBE予測研究
- 上林 敦 (アステラス製薬(株))
- ポストICH M9 時代のジェネリック医薬品開発とは?
- 立木 秀尚 (東和薬品(株))
学術シンポジウム 6 Symposium 6
小児用製剤の開発促進:現状と課題解決に向けた取り組み
- オーガナイザー
- 大貫 義則 (富山大学)
- 原田 努 (昭和大学)
小児医薬品開発の促進に向けた関心や期待は近年ますます高まっているものの、その実現のためには、未だ、技術、経済、規制など多様な問題が存在する。小児患者に優しい薬物医療の実現に向けて、製剤化技術や薬物動態学的な知見など、製剤学・薬剤学の英知が貢献できる部分は非常に大きい。そこで、本シンポジウムでは、臨床、アカデミア、製薬企業などから演者を招き、製剤学・薬剤学的な見地から、小児製剤開発促進に係る問題点や取り組み、問題解決に向けた提言などについて講演いただく。
- 小児製剤に関する国際的課題および小児が服用しやすい製剤について
- 原田 努 (昭和大学)
- 小児医療現場における内服薬の現状と課題
- 楠木 重範 (チャイルド・ケモ・クリニック)
- 小児製剤の設計における留意点と製剤技術
- 髙江 誓詞 (アステラス製薬(株))
- 小児製剤における経口ゼリー剤の製剤設計
- 林 祥弘 (日医工株式会社)
- 小児製剤開発における生物薬剤学的な課題と取り組み:Pediatric biopharmaceutics classification system(PBCS)
- 山下 伸二 (摂南大学)